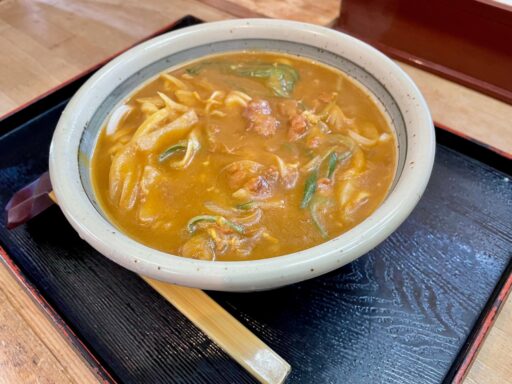収集した薪の処理で忙しくしており、しばらく手がつけられなかった杉の天板加工作業に着手します。改装中の現場からテーブル用の脚4セット(天板二枚分)を持ち帰りました。
刃の直径が260ミリもある大型の丸鋸(マキタ10型マルノコ5201)をお持ちだったので、お借りしました。
天板は一人では移動できないほどの大きさと重さなので、お隣さんの手を借りて、ガレージ内に移動させました。作業用の馬の上に天板を載せると、大きく反っていることが判明。特に左の板。
左の天板を裏返すと中心に割れがあり、両端に鎹が打ってあり、これ以上、割れが進まないようにしてあるのがわかりました。
木工師匠に来ていただき平面の出し方を指導していただきました。私が所有する電気鉋は刃の幅が短くて難儀しそうです。一度も替え刃を交換していないので、切れ味がよろしくないです。木工師匠はこんなにも年輪が詰まった杉は初めて見たと言われていました。寒冷地で育った杉なのでしょうということでした。