テラス屋根軒樋から意図せず雨水が竪樋以外の部分から落下する原因は軒樋が逆勾配になっていたことです。正しい水勾配に戻すことは諦め、竪樋を移設することにしました。しかしながら、妻ばりの部分からも溜まった水が落下する原因は不明のまま。
 AP 7 PIECE BIMETAL HOLE SAW SET
AP 7 PIECE BIMETAL HOLE SAW SET竪樋を西側から東側に移設するには硬い床材に穴を貫通させる必要があります。先日、セール価格で入手したAstro Products製バイメタルホールソーを初めて使いました。
取扱説明書を読んでからBOSCHの振動ドリルに45ミリのホールソーを装着。竪樋の径は42ミリなので、45ミリの穴はちょうど良い。
20ミリ厚のウリン床材に45ミリの穴を空けるのは苦労しそうと思ってましたが、意外と簡単に綺麗な穴を貫通させることができました。バイメタルのホールソーの切れ味が良いのか?
真っ直ぐ下ろした竪樋にエルボーを取り付けて、床に貫通させた穴に通しました。壁面にアルミの雨戸があるので、竪樋を固定することはできませんが、エルボーが床に接しているので、竪樋が下がることはないだろう。
この記事を書いていて、テラス屋根を施工した人に対する疑念が一つ思い浮かびました。このテラス屋根の軒樋がなぜ逆勾配になっていたのか?ひょっとして、軒樋の勾配を調整する方法がわからず、逆勾配になることを知りながら、竪樋が壁面に固定しやすい西側に取り付けたのではないか?軒樋の両端にシーリング材が山のように盛り上げてあるのもそのためか?
この建築物には雨樋が取り付けられていないため、大屋根に降った雨水がテラス屋根に落ちて跳ね返ります。コンクリートに設けられた溝の真上にある大屋根の軒から雨水が落下します。以前はこの部分もウッドデッキでした。床上で跳ね返った水が外壁に当たり、水に弱い杉の羽目板が腐朽する原因となっていました。ここは落差7メートルの滝の下だと思っておいた方が良い。
軒樋の端にある桁キャップを取り除いたら、大量の水が出て来ました。水は桁の中に溜まっていたと思われますが、なぜ桁の中に水が溜まるのかよくわかりません。




Redoing The Deck — Part 15へと続く。
Redoing The Deck — Part 13に戻る。


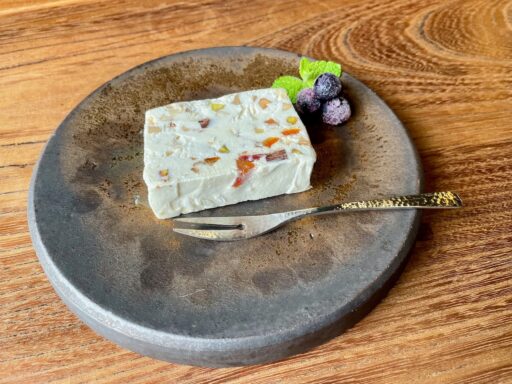























































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f6b9ddf.255528b0.1f6b9de0.e34b744d/?me_id=1350760&item_id=10017229&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fastroproducts-shop2%2Fcabinet%2F20%2F2003000008920_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ee61011.c1f8781a.1ee61012.7f329e12/?me_id=1233038&item_id=10174185&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-partsking%2Fcabinet%2Fsyouhin%2F06165224%2Fimgrc0072287306.gif%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)