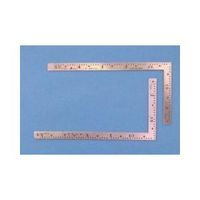初めて訪れた道の駅竜王かがみの里で見かけた剪定用ノコギリがずっと気になっていました。お店のおじさん曰く剪定用ノコギリといえば、プロが愛用するシルキーに限る。Silkyというブランドを知らなかった私はその場でAmazon Appを立ち上げて、通販での販売価格を調べました。お店で販売されていた価格よりも少し安い。通販の方が安く手に入ることを知り、道の駅では購入しないことにしました。
時の経過と共に剪定用ノコギリのことを忘れていましたが、Amazonで貯まっていたポイントの有効期限が迫っていたので、何か欲しいものがないかと物色していると、Silkyのノコギリのことを思い出しました。そのノコギリは木製の柄にキツネの図柄が特徴的でした。Amazonポイントの有効期限ギリギリに発注したそのノコギリが届きました。
Silkyのサイトを調べると、木柄ノコギリのMebae(めばえ)は世界で初めて出来た歯振(あさり)なしのノコギリとのことです。macOS標準Dictionary Appに搭載のスーパー大辞林によると、歯振(あさり)とは「鋸の身と切り口との摩擦抵抗を減らすため、鋸の歯を交互に左右に振り分けること」とあります。このノコギリ、切れ味が驚異的です。
切断面が綺麗。あさりがないノコギリは鋸刄を曲面研磨して鋸自体の厚みであさりを作り出してあるそうです。結果として切断面に傷がつかないという利点があります。感動的ともいえる切れ味以外に、生木の枝打ちをして気付いたことが一つ。木材の切断時に出る木屑が鋸刃の間に溜まるということ。歯が左右に開いているあさり有りの刃だと、切断時の木屑は下に落ちるけれど、歯が左右に開かないあさりなしの刃であれば、歯の間に木屑が詰まるということでしょうか。これはデメリットかもしれませんが、切れ味の素晴らしさを考慮すると、気にならないでしょう。
Silky製品には乾燥木材を切断する大工、DIY用のノコギリ(ヒビキ)も販売されているようです。DIY用のあさりなしのノコギリを使えば、突き出た木ダボの余分を切断する際に、木材表面に傷がつかないという利点もあります。




iMovieの仕様が変更され、以前のようにiMovieからYouTubeに直接、制作した動画ファイルをアップロードできなくなりました。制作した動画ファイルはローカルディスクに一旦、書き出してからブラウザー経由でYouTubeにアップロードのようです。