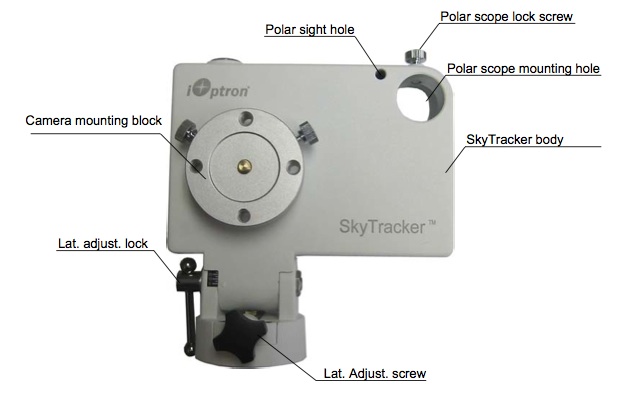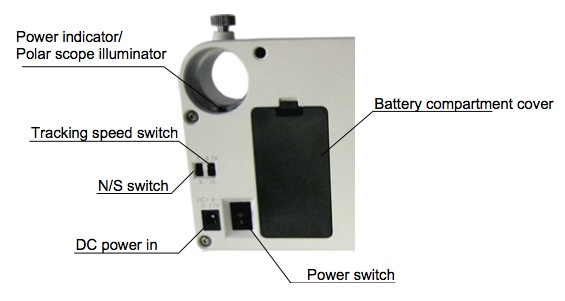雪が降る自宅を出発したのは午前9時前、「モータースポーツファン感謝デー」が開催される鈴鹿まで行けば、天気予報通りに晴れるだろうと期待しつつサーキットに到着したのが10時半頃。この日は終日、太平洋岸の鈴鹿も雪が降ったり止んだりで風が強い寒い一日でした。

今回の主な目的は昨年末に入手したNikon D7000のモータースポーツ撮影。もちろん、今年からアジアに出て行くFポン(Formula Nippon)改め、Super Formulaのマシンを見てエンジン音を楽しむことも目的です。SF(Super Formulaの新しい略語)開幕戦と最終戦にHondaエンジン搭載のTeam Mugenからスポット参戦する佐藤琢磨が、ラウンド0とテスト走行のために鈴鹿にやって来ると言うことでそちらも楽しみ。

この日、ISOはオートで上限が1600~3200、シャッタースピードの下限が1/30秒に設定していましたが、絞り優先で人物が被写体の場合、被写体ブレが起こる可能性があるので、翌日は下限を1/40秒に設定し直しました。

サーキットに持参したレンズはAF-S NIKKOR 70-300 f/4.5-5.6 G EDのみ。同行者はSony DSC-RX100。70mmからの望遠レンズなので、私が撮るピットに展示中のマシンは全体像を撮影することができません。被写体から離れると、人の山が視界を遮ります。ピットウォーク、グリッドウォーク時は大勢の観客が往年のマシンを近くで見ようと集まっています。

センターハウスのある側の人混みはそれほどでもありません。

SUZUKA-ZEで昼食を済ませ、「時空を超えたF1日本GPデモラン」に登場するマシンを撮影するため、トンネルを通ってダンロップコーナーのあるE席、カメラマンエリアへと向かいました。ここは流し撮りには向いていないので、1/500秒の高速シャッターで撮影。

1990年日本グランプリで3位表彰台を勝ち取ったLola LC90に乗る鈴木亜久里ご本人。エンジンはLamborghini V12。E席にいる観客のほとんどがカメラマンなので、手を振ってくれても、撮影に忙しくて応えられません。

斜め方向にカメラを振る流し撮りは難易度が高いですが、ぴたっと決まれば達成感が得られます。なぜかFerrari F2003のレッドは、オレンジに写ってしまう。この日はRAWで撮影しましたが、Apertureで補正できないほど、実際の色とは異なります。ドライバーは中野信治。

上のLotus 72Eの写真、F1マシンデモ走行中の流し撮りとしては控えめなシャッタースピード(1/250秒)ですが、意図したところにピントが合っていません。Nikon D7000の使用説明書によると、AFエリアモードの設定ではダイナミックAF 9点が、「被写体の動く方向が予測でき、フォーカスポイントで被写体を捉えやすい撮影に適しています。(例:陸上競技やモータースポーツ)」と書いてあるので、9点のオートフォーカス且つAF-Cに設定しました。この設定が不適切だったような気がしたので、翌日はシングルポイントAFに変更しました。

鈴鹿F1日本GP25回記念「1987年F1の衝撃」は、パドックにあるホスピタリティーテラスに移動して撮影しました。ホームストレートを真横から見ることになるので、ここは流し撮りモード全開。焦点距離は165mm。(換算247mm)このぐらいがレンズの解像感を維持する限界かもしれません。Tyrrell 019を操るドライバーは先月、還暦を迎えたばかりの中嶋悟。この時代からEPSONがスポンサーになっています。

左から65歳の星野一義、現役ドライバーの佐藤琢磨、そして当時の青いレーシングスーツを着ている中嶋悟。来年、F1マシンは再びターボエンジンを搭載することが決まっていますが、McLarenにホンダがエンジンを提供するかもしれないとする噂があるようです。そうなれば、佐藤琢磨にMcLarenのドライバーとしてF1に復帰してもらいたいものです。

グランドスタンドの観客を背景に記念撮影するということで、パドックの方にいる我々の方を向いてくれました。レンズは望遠端の300mm。(換算450mm)

3階のホスピタリティーテラスから下り、ピット後方を歩いていたら、突然目の前に佐藤琢磨。琢磨ファンの同行者はミニバンのところまで追いかけて行き、広報担当者と共に車に乗り込んだ佐藤琢磨に向かってミニバンのすぐ横で何度も手を振ったら、何度も手を振り返してくれたそうです。
この後、CS Fuji NextのF1中継で解説をしておられる小倉茂徳氏にも出会いました。小倉さんのファンでもある同行者が話しかけたら立ち止まってくれました。記念撮影にも応じてくださいました。今年は主に金曜の練習走行時に解説するそうです。小倉さんの解説は、下調べを十分にしている人でないとできないわかりやすい解説です。

二輪は全部、同じように見える私には撮影した写真を説明することはできません。

上半身を起こしたり、寝かせたりして風の影響を調節しているように見えます。この画像撮影時はアクセル全開でしょうか。

鈴鹿8耐&鈴鹿1000kmトワイライトデモンストレーションレースのフィナーレ。夕暮れ時の撮影には慣れていますが、サーキットを照らす明るい照明がないので、シンガポールGPナイトレースよりも暗い。花火とヘッドライトの光を避けて測光しないと画像が暗くなります。

高感度熱ノイズのように写った白っぽい斑点は雪。