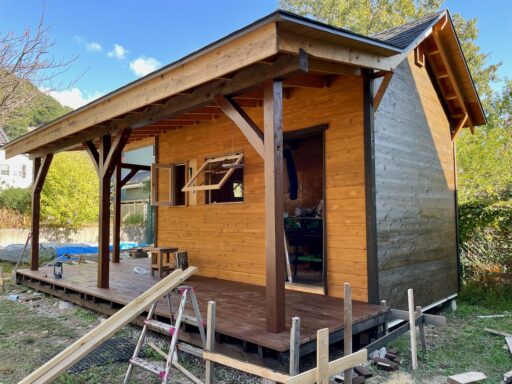およそ5ヶ月ぶりにSuzuki HUSTLERのエンジンオイルとフィルターを交換しました。
これまではAstro Products製オイル処理ボックス4.5L等に廃油を入れて、可燃ごみとしてゴミの日に出していました。そのオイル処理ボックスが徐々に値上げされていて、4.5Lのボックスで税込451円もすることがわかりました。行きつけのガソリンスタンドで尋ねてみると、自分でオイル交換した際に出るエンジンオイルの廃油をありがたいことに無償で引き取ってくれるとのことでした。

ということで今回、初めて15Lのオイルパンに廃油を受けた後、ペール缶に移し替えて、ガソリンスタンドに持って行きました。
集めた廃油は定期的に業者が回収に来られるそうです。
総走行距離:83,002km
前回交換時からの走行距離:5269.6km