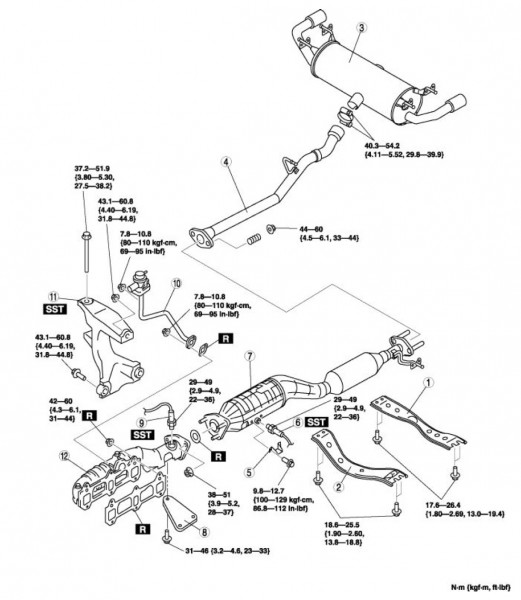Mazdaディーラーのお勧めに従い、点火プラグを新品に交換しました。使い古したNGK純正プラグから新しいNGK純正相当プラグ(RE7C-L2本とRE9B-T2本)への交換になります。新品プラグはパッケージと品番が米国仕様になっているだけで、製品自体は同じものと思われます。
今回は英文整備マニュアルを入手したので、マニュアル記載の正しい手順を参考にしながらスパークプラグの交換を行いました。整備士用マニュアル記載の手順とは下記の通り。
- エンジンカバーを取り外す。(すでに取り外してありました。)
- バッテリーカバーを取り外す。
- バッテリーのマイナス側端子の接続を切る。(普段、これはやっていません。)
- プラグケーブルのスパークプラグ側端子を取り外す。
- プラグレンチを用いてスパークプラグを取り外す。
注意:白の塗料で印したスパークプラグをリーディング側に取り付け、青の塗料で印したスパークプラグをトレーリング側に取り付ける。
注記:一部のスパークプラグは車両下方から作業した方が取り外しやすい。 - 取付時は取り外した時の逆の順。
締付トルク値は12.8〜17.7 N•m
上記手順は整備士用の手順であり、サンデーメカニックである私にはもっと詳しい手順が必要です。
- エンジンフードを開けてエンジンカバーを取り外す。
- バッテリーカバーを取り外す。
- バッテリーのマイナス側端子の接続を切る。
- ジャッキアップして左前輪を取り外す。
- 左前輪タイヤハウジング内にあるゴム製ガードの片方を外す。
- トレーリング側プラグケーブル2本を手前に引き抜くようにして外す。
- 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+全長265mmのT型ハンドルを用いてトレーリング側の古いスパークプラグ2本を取り外す。
- 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+プリセット型トルクレンチを用いてトレーリング側の新しいスパークプラグ2本を規定の締付トルク値(12.8〜17.7 N•m)で締め付ける。
- トレーリング側プラグケーブルを元に戻す。
- リーディング側プラグケーブル2本を手前に引き抜くようにして外す。
- 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+全長265mmのT型ハンドルを用いてリーディング側の古いスパークプラグ2本を取り外す。
- 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+プリセット型トルクレンチを用いてリーディング側の新しいスパークプラグ2本を規定の締付トルク値(12.8〜17.7 N•m)で締め付ける。
- リーディング側プラグケーブルを元に戻す。
- 左前輪タイヤハウジング内にあるゴム製ガードを元に戻す。
- 取り外した左前輪を元に戻す。
- バッテリーのマイナス側端子を接続する。
- バッテリーカバーとエンジンカバーを元に戻す。
- DSCが適切に作動するように、ステアリング・アングル・センサー初期化の手順を実行する。
ステアリング・アングル・センサー初期化の手順は以下の通り。
- マイナス側バッテリーケーブルを接続する。
- イグニションスイッチをONにする。
- DSC表示が点灯し、DSC OFFが点滅するのを確認する。
- ステアリングホイールを右にロックするまで回し、その後、左にロックするまで回す。
- DSC OFFの表示が消えるのを確認する。
- イグニションスイッチをOFFにする。
- イグニションスイッチを再度、ONにしてDSC表示が消えるのを確認する。
スパークプラグを取り外す時に使用したハンドツール。左から21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント(TONE BJ30)+150mmのエクステンションバー(Koken 3763-150)+100mmのエクステンションバー(Snap-on FXK4)+全長265mmのT型ハンドル。
スパークプラグを取り付ける時に使用したハンドツール。左から21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+150mmのエクステンションバー(Koken 3763-150)+100mmのエクステンションバー(Snap-on FXK4)+東日製作所モータースポーツ用プリセット型トルクレンチ。
締付トルク値は規定内の15.5N•mで締め付けました。かなり、緩めです。
1月2日からおよそ3ヶ月が経過し、漸く溶損した触媒とO2センサー、点火プラグの新品交換作業が完了しました。点火プラグの交換後、エンジン始動は一発、エンジン不調が発覚した時の前の状態と言うより、数年前の快調な状態に戻ったような感じがします。
プラグを新調してからの新しい触媒の印象はどうかと言うと、音が静かになったような気がします。新車の頃の音に近いかもしれません。壊れた純正触媒と比較するのも適切ではありませんが、カラカラ音がなくなり、マフラーからボッ、ボッ、ボッの音もなくなりました。5,000 rpmを超える高回転はまだ試していませんが、外からのエンジン排気音がより静かになった分、車内に置いてあるもの(iPad用のホルダーなど)が干渉する音や、タイヤの音が目立つようになりました。
改めてエンジン不調の原因を考えてみると、Mazdaディーラーの担当整備士が言われていた通り、根本的な原因は車外品のレーシングプラグとその使い方にあったようです。濡れたプラグの失火を起因として、未燃焼の混合気が触媒内部で燃えていたということになります。車両火災には至らなかったものの燃えては行けないところで燃えていたわけですから、危険な状態にあったはずです。事実、エンジンルームから白煙が上がっていたわけで、火災の一歩手前だったかもしれません。
作業の難易度:5段階で3