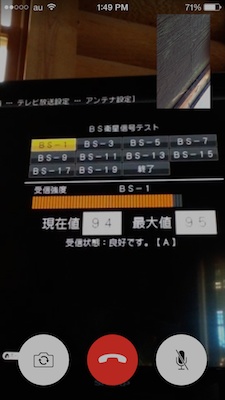カーオーディオの音質を向上させることができるPanasonic Blue Battery “caos”に交換したMazda RX-8で長距離走行しました。バッテリーが新しくなり、エンジン始動が改善しました。加速性能も心持ち、良くなったような気がしますが、多分プラシーボ効果です。
RX-8 Type SにはBoseサウンドシステムが標準装備されています。リアシェルフの下にデジタルアンプ。
その左右に5cmのミッド・ハイレンジのスピーカー2個と15 x 23cmのウーファー2個。インストルメントパネル中央に8cmのミッド・ハイレンジのスピーカー1個、フロントドアに5cmのミッド・ハイレンジのスピーカー2個と専用のスイッチング変調アンプ付き23cmのNd®ウーファー2個が搭載されたシステムになっています。合計するとスピーカー5個にウーファー4個とリビングルームのオーディオシステムよりも立派な装備になっています。
ステアリングコラムの横にはAudioPilot™システムで使われる専用のマイクロフォンも搭載されており、走行時の騒音レベルに応じて自動的に音質と音量を変化させることができます。
ブルーバッテリー”caos”に交換したことにより、オーディオの音質はどのように向上したのか?率直に言いますと、音質の向上は私の耳ではほとんど感知できずでした。変化があったかもしれないとしたら、小音量の時の音質です。Subaru R1とSuzuki Jimnyでは大きな音質向上が確認できましたが、元々、優れた音質であったRX-8の場合はさらに音質を向上させることは難しいというところでしょうか。
Panasonic® Blue Battery “caos” 125D26L for Mazda RX-8 — Part 1に戻る。